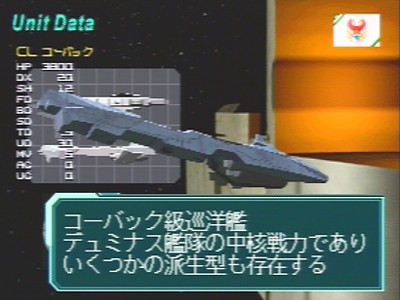
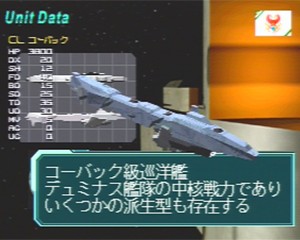
| ■独立新軍の中核として建造された重装汎用艦 デュミナス王国 巡洋艦コーバック級 |
|
KDF, Light Cruiser "COARVECK"
class
2006/3/19 Ver.1.0 |
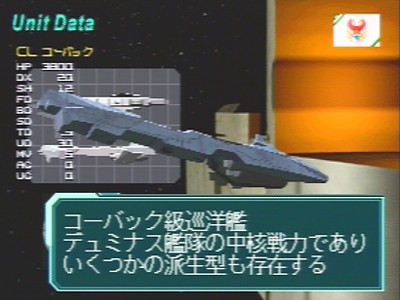 |
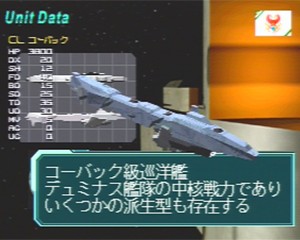 |
| ■DATA (第二期生産型計画値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
>>コーバック>> |
|
|
コーバック級巡洋艦はデュミナスが初めて自国単独で設計・製造を行った戦闘艦である。 |
|
| デュミナス王国が宗主国であるアマティスから独立したE.G.990年時、同国が保有する宇宙戦力の中心となったのは、アマティスから譲渡、もしくは購入されたベルナルド級巡洋艦とオルオーク級駆逐艦であった。
この二種は当時最新鋭と言ってよい艦艇であったが、同時期他国では技術進歩にあわせた新規設計の艦艇が次々と計画されつつあり、いかに高性能艦であろうと早晩戦力不足に陥ることが予想された。 同級の計画が正式に立てられたのは、軍事技術の蓄積・整備を目的とした「第一次宇宙艦隊整備計画」の達成を控えたE.G.996の中頃のことで、その主目的は、二年後のE.G.998年に開始されることになる「第二次宇宙艦隊整備計画」の中で、デュミナス宇宙軍の主力戦闘艦の立場を担うことにあった。 同年、王立宇宙軍内部に宇宙軍少将を長とする「次期主力巡洋艦規格決定委員会」(通称レッド委員会)が設立され、次世代戦闘艦の有るべき姿を求めて様々な討論が行われている。 半年の研究の結果、新巡洋艦は、 従来の巡洋艦は(2)と(3)の要素を重視し、領域警備や偵察に就くためにた長い航続力と多数の数が重要とされていたが、デュミナスの次世代艦が必要としたのは以上の二つの他に高い戦闘能力をも必要としたわけである。 この困難な要求の解決に当たる設計部に王立宇宙軍が指名したのが、王立宇宙軍艦船設計部(後の王立宇宙軍艦政本部)と民間のフェルミア造船局双方の人員で構成された特別プロジェクトチームであった。 *〈ベルナルド〉級巡洋艦* *〈オルオーク〉級駆逐艦* *第一次宇宙艦隊整備計画* *第二次宇宙艦隊整備計画* *「次期主力巡洋艦規格決定委員会」* >>ベルナルド級巡洋艦>> >>オルオーク級駆逐艦>> >>第一次・第二次宇宙艦隊整備計画>> |
|
|
過酷な要求であったものの、官民合同のプロジェクトチームは2ヶ月の後に次期巡洋艦の設計案としてCX−1からCX−3までの三案を纏める事に成功していた。 この内、CX−1案は搭載する主砲を他国の同級艦より増やした案で、火力の投射回数を多くすることにより対象の防御シールドを早期に破壊する事を目的とした艦であった。 この三種の案はそれぞれ長所と短所があり、「レッド委員会」の中でそれぞれの案を押す派の間で採用を巡って後に「巡洋艦論争」と呼ばれる大論争に発展したのだが、半年の後、最終的に外宙を航行可能な重装雷撃巡洋艦であるCX−3案が採択されることとなった。 *アサルトドローン* *ナバモス* >>巡洋艦論争>> >>レッド委員会とCX−3案>> >>バナモス>> |
|
|
・船体スタイル コーバック級は、単胴式の船体と、船体上部に配された主砲群、その後方に置かれた艦橋、そして艦後部に設置された機関、というE.G.990年代に一般化したスタイルが採用されている。これは同級が初めて自国設計・製造である事に対しての不安が拭い去れなかったことから堅実なスタイルとして計画されたためである。 ・船体構造 ライセンス等で手に入れた規格の違う武装を搭載するためと、テレダイン級と艤装の共通化を行うべく、ユニット・ブロック(パッケージ)工法を大規模に採用している。これにより同級は外見に差が無くとも事実上別の艦と言うべき派生型が存在することになった。 ・武装 中期型以前の艦には艦上部にレーザー砲とミサイルのどちらかを搭載可能な汎用ターレットを2基設置していたが、後期型以降の艦では艦下部の死角をなくすべく同部にレールガン砲座を1基設置し砲撃範囲を拡大した。このとき、艦上部の汎用ターレット部は可動式のレーザー砲座とし、ミサイル兵装も艦内部に収納するよう改設計されている。 ・防御関連 単殻式構造を採用しているため一撃の威力のある大口径砲からの対弾性は十分とは言えないが、各ブロック事に有る程度の装甲が張られていることで小口径砲の連続した打撃に対しては十分な耐久性を有する。 ・機関関係 大出力機関を搭載することで、他国巡洋艦と比較して巨大な船体を有しているにもかかわらずほぼ同等の重量推力比を維持しており、十分な加速力を有している。反面、チャージ性能ではやや劣っており、再度のチャージに時間が掛かるようになっている。 ・航空兵装 中期型以前の艦では警備・索敵用途のため艦下部に小型の格納庫を持ち、少数ながら一応の艦載機運用能力を有している。しかし、後期型では機体下部の艦載機整備スペースに砲座を設置したため武装変更や修理を行うことが制限されている。 ・航続距離 外宙での迎撃を行うために十分な期間を航行可能な長い航続力を有する。後に製造された艦ほど暫減作戦のためによりいっそうの航続力の伸張が行われている。 ・その他 住居ブロックを初めとする各種艤装がテレダイン級駆逐艦と共有化されており、その結果個艦当たりの調達コストの低減化に成功している。 ・総合評価 個艦優越主義で知られるデュミナスとして、高い戦闘能力や機動力の他、他艦種との艤装の共通化によるコストダウンや、AD兵器搭載による重火力の確保といったコンセプトが高く評価されている。
*ユニット・ブロック工法(パッケージ工法)* >>ユニット・ブロック工法>> |
|
|
コーバック級は一番艦の竣工から長期にわたっていることもあり、幾度か設計が見直されている。これらは製造次期によって大きく以下の五つに分類する事が出来る。 ・「初期生産型」 第二次宇宙艦隊整備計画において製造されたタイプ。すべての基礎になった型である。艦上部に2基のターレット(基本的にDLG45及びGMM40が搭載された)とADバナモスを搭載し、2機の艦載機を運用することが可能となっている。生産艦の一部はAD兵器を搭載せず、代わりに旗艦施設を設置したものがある。 ・「第二期生産型(前期型)」 第二次長期軍備計画の中で製造されたタイプで、艦載機の運用能力を強化するために初期型に比べわずかに船体を拡張している。これにより、艦載機の運用可能数が3機となった。また、船体改設計とあわせて艦内配置の見直しが行われ艤装の一部省略化が行われた。また、このとき主砲をDLG45からDLG47にアップデートしている。 ・「第三期生産型(中期型)」 第二次長期軍備計画の後期から第三次長期軍備計画の初期にかけて起工されたタイプで、巡洋艦としての性能を高めることに重点が置かれた。汎用性を高めるため、第二期建造艦より大きく艦容積が増している。 ・「戦時急造型(後期型)」 第三次長期軍備計画の中で建造されたタイプ。デトロワとの戦争を睨んで大量発注されており、中期型と略同型であるが、生産性と省力化をより一層高めるため、武装は完全に規格化される事になった。これにより艦上部の汎用ターレットが廃止され、代わりにDLG57専用砲座とし、GMM70対艦ミサイルを艦内部に再配置している。同時に、航空艤装が縮小され、代わりにレールガンを船体下部に搭載した。 ・「最終型」 デュミナス本星解放後から製造が開始されたタイプで、E.G.1028現在も建造が続いている。デュミナス戦役以降の戦争によって消耗した戦力を再整備するため、まとまった数が起工されているが、現在開催中のフェール軍縮会議の決着次第では大幅に建造が取りやめられる可能性もある。
*デュミナス戦役* *第一次星系大戦* *第二次星系大戦* *フェール軍縮会議* >>第一次・第二次星系大戦>> >>フェール軍縮会議>> |
|
|
コーバック級は様々な派生型が存在している。これは、同級が特別な改造を行うに適当な大きさを持っているためであろう。 ・A型 基本型前期型 初期計画の中で、標準型として最も生産される予定だった型。主砲2基の他に2機の艦載機運用能力を有する。初期生産型の主力である。 ・B型 基本型後期型 A型の改良型で、格納庫を拡大し艦載機搭載数を2機から3機に強化した型。前期型から中期型にかけて採用されている生産中核である。 ・D型 突撃型 船体下部の艦載機格納庫を縮小し、代わりにレールガンを搭載したもの。全周囲に火力を指向できる艦隊戦闘型として、後期型以降の主要生産型となった。 ・S型 偵察型 B型をベースに航空機の運用が可能なように大型格納庫を装備したタイプ。常用として3機、補用を含めると6機の艦載機運用能力が与えられており、索敵や後方攪乱に威力を発揮した。デュミナス解放軍では間接打撃集団に集中配備され、多大な戦果を挙げている。 ・V型 航空艤装強化型 S型の良好な実績をうけて、さらなる運用機数の増加を計った型。船体下部にS型の三倍近い格納庫を設置し、常用12機、補用6機という戦艦級の艦載機運用能力を持つ。しかし、船体スペースの関係から航空指揮能力の強化が殆ど行えなかったこと、重量増加によって速力が低下したこと等が重なったため、個艦レベルでは予定していたほどの性能強化とはならなかった。星系大戦では軽空母的運用が行われている。 ・F型 指揮機能強化型 テレダイン級駆逐艦を多数指揮する必要性から、指揮機能を強化したもの。艦橋が大型化し、高い嚮導能力を得た。生産時期によってB型とD型がベースとされている。艦事に改装内容に微妙に差があり、AD搭載を諦めたものや艦載機格納を諦めたものなどがある。 |