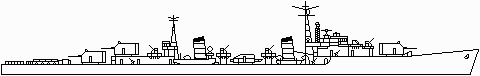
| 擔杮奀孯丂娡戉宆嬱拃娡乹彫弔乺媺乛壜宆 |
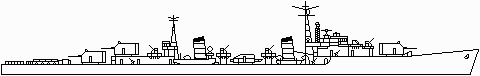 |
| 恾偼乹彫弔乺嘥宆擇斣娡乹弶壒乺 |
丂懳撈愴傪嵘傫偱寶憿偝傟偨娡戉宆枩擻嬱拃娡劅劅乹孫晽乺媺嬱拃娡偼丄崅偄惈擻傪摼傞偨傔婎弨攔悈検偑3250僩儞偵払偡傞戝宆嬱拃娡偲側偭偰偟傑偭偨丅偟偐偟丄偙偺傛偆側娡傪寶憿偡傞偨傔偵偼懡偔偺旓梡偲帪娫偑昁梫偱偁傝丄曗彆娡偵偲偭偰嵟傕廳梫側梫慺偱偁傞乽悢傪偦傠偊傞乿偙偲偼崲擄側傕偺偲側傜偞傞傪偊側偐偭偨丅
丂偦偺偨傔擔杮奀孯偼娡戉宆嬱拃娡偺惍旛傪丄桳椡側惈擻傪帩偮僴僀丒僐僗僩側乹孫晽乺媺嬱拃娡偲丄彫宆偱検嶻偑棙偔儘乕丒僐僗僩偺嬱拃娡偲偺擇杮棫偰偱惍旛偡傞偙偲傪寁夋偟偨丅偙偺儘乕丒僐僗僩嬱拃娡偑丄乹壜乺宆嬱拃娡偲偟偰抦傜傟傞乹彫弔乺媺偱偁傞丅
丂摨媺偺愝寁偵摉偨偭偰偼丄僐僗僩僟僂儞偲戝検惗嶻偺偨傔偵揙掙揑側娙慺壔偲崌棟壔傪恾傞偨傔偵捈慄偲墌偱峔惉偝傟偨慏懱傪嵦梡偟偰偄傞丅傑偨丄婡娭偼乹弶弔乺媺偺傕偺傪棳梡丄旛朇偦偺懠偺鋨憰昳偺幍妱嬤偔傕乹徏乺媺嬱拃娡偲嫟捠偲偟偨丅傎偐偵丄寶憿岺朄偲偟偰揹婥梟愙偲僽儘僢僋岺朄傪庢傝擖傟傞偙偲偱戝暆偵寶憿僗僺乕僪傪忋徃偝偣傞帠偵傕惉岟偟偰偄傞丅偝傜偵丄嵽椏偲偟偰擖庤偺梕堈側崅挘椡峾傪巊梡偡傞帠偱惗偠傞廳検憹壛傕栚傪偮傇傞帠偲側偭偨丅偙偆偟偨搘椡偵傛偭偰乹彫弔乺媺偺寶憿偵昁梫側婜娫偼暯嬒偱敧儢寧偲偄偆懍搙傪婰榐偟偰偄傞丅
丂惗嶻惈傪廳帇偟偰愝寁偝傟偨乹彫弔乺媺偼丄徍榓擇嶰擭堦擇寧偵撍擛偲偟偰巒傑偭偨擔暷愴偺偨傔丄戝宆娡偺寶憿丄廋棟偱梋桾偑懚嵼偟側偐偭偨姱塩岺応偵曄傢偭偰慡崙偺柉娫憿慏強偱戝憹嶻偑峴傢傟傞帠偲側偭偨丅偙偺偲偒丄朇側偳偺鋨憰昳偺搒崌偑晅偐側偄娡偑弌偨偨傔丄怴媽條乆側晲憰傪娫偵崌傢偣偱憰旛偡傞帠偵側偭偨乮偦偺偨傔丄堦晹偱偼搵嵹暫憰偑敋棆偺傒偲偄偆娡傑偱弌尰偟偰偄傞乯丅
丂摉弶偺梊掕偱偼擇慄媺晹戉偲偟偰屻曽巟墖偵廬帠偡傞偼偢偺乹彫弔乺媺偱偁偭偨偑丄愴憟偺塭嬁偵傛偭偰弙岺偡傞曅抂偐傜嵟慜慄偵搳擖偝傟丄傎偲傫偳偺愴摤偵巓枀娡偺偄偢傟偐嶲壛偟偰偄傞丅
丂側偍丄愴屻偵側偭偰摨媺偼乽偦傟傎偳桪廏偱偼側偐偭偨乿偲偄偆晽愢偑堦斒壔偡傞偙偲偵側偭偨偑丄乹彫弔乺媺偵媮傔傜傟偰偄偨栶妱偼戝宆嬱拃娡偺曗姰偱偁傝丄偦偆偄偭偨揰偐傜偼傓偟傠廫暘側寢壥傪巆偟偨偲偄偊傛偆丅
丂愴屻偼孯旛弅彫偺梋攇傪庴偗偰傎偲傫偳偑夝懱丄偁傞偄偼梊旛娡偲偝傟丄忬懺偺椙偄偛偔彮悢偺傒偑尰栶偵巆偭偨丅巆傝偼桭朚崙偵攧媝乮戄梌乯偝傟偰偄傞丅
丂仩梫栚乮乹彫弔乺嘥宆丂寁夋抣乯
丂丂仭婎弨攔悈検丂1960t丂丂仭慡挿丂丂丂丂119.4m丂丂仭慡暆丂丂丂10.5m
丂丂仭嵟戝懍椡丂丂32.4kt丂 仭婡娭弌椡丂丂42000hp丂 仭峲懕椡丂丂4000M/18kt
丂丂仭庡梫暫憰丂丂45岥宎巐幃12.7噋楢憰崅妏朇俁婎
丂丂丂丂丂丂丂丂丂70岥宎屲幃40噊婡廵侾俆栧乮嶰楢憰俆婎乯
丂丂丂丂丂丂丂丂丂楇幃61噋屲楢憰嫑棆敪幩娗侾婎
丂丂丂丂丂丂丂丂丂巐幃嶶晍敋棆壋俀婎
丂仩梫栚乮乹彫弔乺嘨宆丂寁夋抣乯
丂丂仭婎弨攔悈検丂2125t丂丂仭慡挿丂丂丂丂121.2m丂丂仭慡暆丂丂丂10.5m
丂丂仭嵟戝懍椡丂丂32.2kt丂 仭婡娭弌椡丂丂42000hp丂 仭峲懕椡丂丂4000M/18kt
丂丂仭庡梫暫憰丂丂45岥宎巐幃12.7噋楢憰崅妏朇俁婎
丂丂丂丂丂丂丂丂丂70岥宎屲幃40噊婡廵俀侽栧乮巐楢憰俆婎乯
丂丂丂丂丂丂丂丂丂楇幃61噋屲楢憰嫑棆敪幩娗侾婎
丂丂丂丂丂丂丂丂丂巐幃嶶晍敋棆峛俀婎
丂仩摨宆娡丂丂丂丂堦巐巐惽乮夵椙宆丄弨摨宆娡傕娷傓乯
| 忋傊栠傞乛恑傓 | MILITARY偺僩僢僾儁乕僕傊 | index儁乕僕傊 |