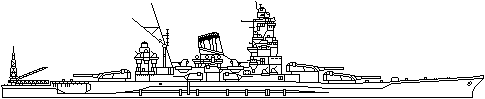
| 擔杮奀孯丂弰梞愴娡乹屷嵢乺宆 |
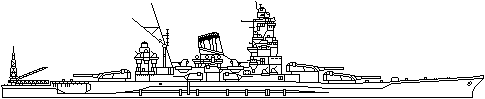
| 仭 Data 乮懢暯梞愴憟奐愴帪丒恾偼怴憿帪偺傕偺乯 |
|||||
| 婎弨攔悈検丗 | 36000t | 枮嵹攔悈検丗 | 42600t | ||
| 慡挿丗 | 242.0m | 慡暆丗 | 32.0m | 媔悈丗 | 9.3m |
| 婡娭丗 | 娡杮幃僆乕儖丒僊儎乕僪丒僞乕價儞俉婎係幉 | ||||
| 弌椡丗 | 150000hp乮寁夋帪乯 | ||||
| 嵟戝懍椡丗 | 32.2kt | 峲懕椡丗 | 7870M/16kt | ||
| 庡梫暫憰丗 | 50岥宎嬨榋幃35.6噋嶰楢憰朇俁婎 | ||||
| 65岥宎嬨敧幃10噋楢憰崅妏朇侾侽婎 | |||||
| 65岥宎屲幃40噊婡廵俁俀栧乮巐楢憰俉婎乯 | |||||
| 70岥宎榋幃20噊婡廵俁俇栧乮巐楢憰係婎丄楢憰係婎丄扨憰侾俀婎乯 | |||||
| 屲幃12噋嶰乑楢憰懳嬻暚恑朇係婎 | |||||
| 摨宆娡丗 | 乹屷嵢乺乹忢斨乺乛乹堦堦乑崋娡乺乹堦堦堦崋娡乺乮寁夋偺傒乯 | ||||
| 堦偮忋偺奒憌傊 | index儁乕僕傊 | 憤崌index儁乕僕傊 | 堦偮慜傊 |